「米国債の利回りが上がってるし、CFDで長期保有すれば金利収入で儲かるはず」──
そんな期待で米国債CFDを買ったのに、気づけば損失が積み上がっていた……。
実はこの現象、CFD特有の“仕組み”による当然の結果かもしれません。
本記事では、債券CFDがなぜ長期保有に向かないのかをわかりやすく解説。
現物債券との違いや、損を避けるための活用方法についてもご紹介します。
はじめに:債券CFDは「高金利=有利」じゃない?
アメリカの金利がこんなに高いなら、米国債CFDを買っておけば金利収入で儲かるはず。
米国10年債の利回りが4%なら、レバレッジ3倍で年12%!?
──そんなふうに考えていた時期が、私にもありました。
ところが、債券CFDを長期保有すると、金利が高い局面でも逆にパフォーマンスが悪化するケースがあるのです。
なぜそんなことが起きるのか?その仕組みを解説していきます。
債券CFDの正体:原資産は“債券先物”
多くのCFDは、実際には対象となる先物に投資しています。
債券CFDも例外ではなく、たとえば「米国10年債CFD」は米国債先物の価格をもとに作られています。
つまり、本物の債券を買っているわけではないという点が重要です。
この「先物ベース」という点が、状況によっては長期保有に不利な構造となってしまう理由です。
債券先物にひそむ罠:やっかいな短期金利
先物に投資するということは、短期金利でお金を借りて対象となる資産に投資しているのと同じ意味を持ちます。
つまり、債券CFDに投資するというのは、「短期金利で借金して、長期金利で運用する」というポジションをとっているのと同じなのです。
このとき、短期金利のほうが長期金利より高ければ──
“借金して運用しても利回りがマイナス”という、逆ザヤの状態になってしまいます。
具体例:米国10年国債CFDの利回り
仮に、米国の金利状況が以下のようだったとします。
- 短期金利(政策金利ベース):5.0%
- 長期金利(10年債利回り):4.0%
この状態で債券CFDを保有すると、年率1.0%分のコストが継続的に発生します。
これは、「価格調整額」の支払いとして投資家に重くのしかかってくるわけです。
保有しているだけで資産が目減りしていく──
債券CFDの長期保有が“報われない”理由がここにあります。
債券CFDが使える場面とは?
もちろん、債券CFDが完全に悪者というわけではありません。
以下のような目的や場面では、有効な投資手段となり得ます。
- 短期的な金利変動を狙うトレード(例:利下げ見通しで米国債ロング)
- 株式ポートフォリオのヘッジ目的
- 長短金利差がプラス(長期金利 > 短期金利)のときに
これらの目的や場面では債券CFDを使うことができます。
特に注目したいのが、「長短金利差がプラスのとき」
たとえば、2008年のリーマンショック後や2020年のコロナショック時のように、FRBが政策金利を一気に引き下げると、「長期金利 > 短期金利」という状態になり、債券CFDの構造が投資家に有利に働きます。
実際、当時の米国債CFDは、ロールオーバーでプラスの価格調整額が入る「長期保有でコストが利益に転じる」という状況となっていました。
つまり、債券CFDは金利構造が“順イールド”という条件下であれば、長期保有でも有利になることがあるのです。
💡 用語解説:順イールド・逆イールドとは?
債券の世界では、期間の長い国債ほど金利(利回り)が高いのが普通です。
このように「長期金利 > 短期金利」の状態を順イールド(正常な利回り曲線)と呼びます。
一方で、将来の景気後退が予想されると、短期金利の方が長期金利より高くなることがあります。
これが逆イールドで、「景気後退のサイン」としても注目される現象です。
まとめ:債券CFDは「長期保有には不向き」な商品です
債券CFDは、見た目こそ「米国債」ですが、先物価格をベースに設計された別モノです。
そして先物には「短期で借りて長期で運用している」という前提があるため、
短期金利が高い局面では、保有しているだけで損をしやすい仕組みになっています。
債券CFDは短期売買・ヘッジ・長短金利差がプラスのときにこそ向いている──
そう理解して使うことが、損をしないための第一歩です。
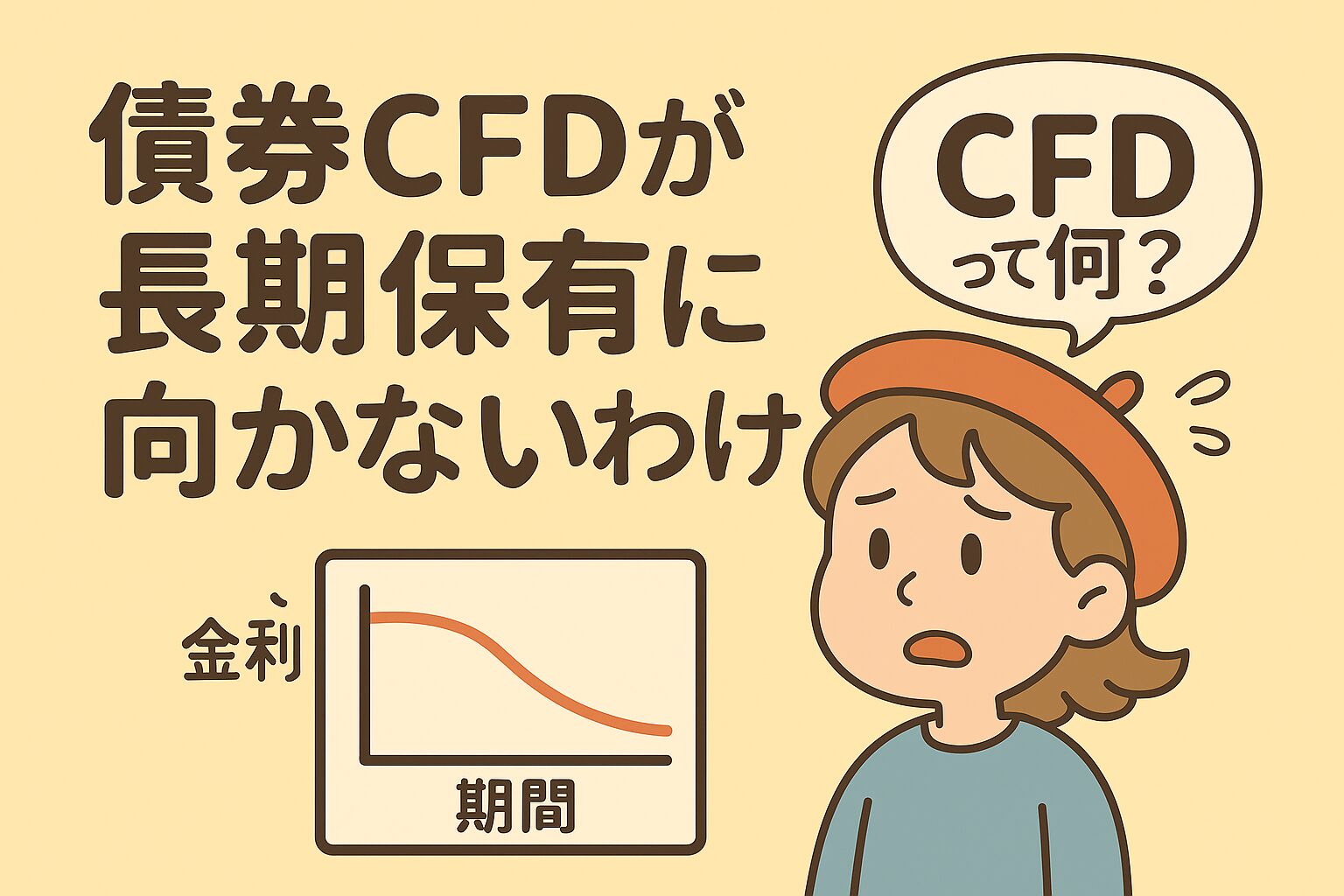


コメント